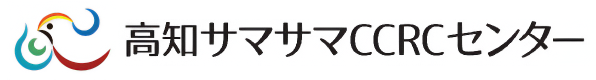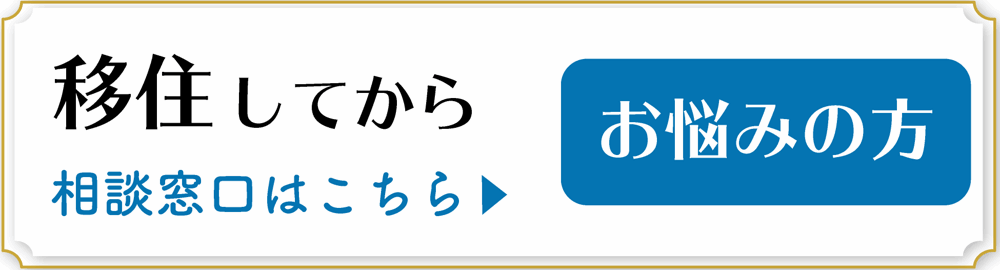高知移住者インタビュー

東京で、海外での「サマサマ経験」を経て高知にUターン
カフェバーSAMASAMA オーナー
井倉俊一郎
■1951年 高知県土佐清水市生まれ
■1972年 株式会社京王プラザホテル入社
ミクロネシアサイパンインターコンチネンタル、インドネシアジャカルタインターコンチネンタルホテルと6年間にわたる海外ホテル勤務を経験
■1993年 株式会社京王プラザホテル退社
■高知にUーターン
現在 九反田テラス2Fにて 「カフェバーSAMASAMA」を経営
■認定NPO高知インドネシア看護師サポート会 理事

生まれは昭和30年代。日本の秘境と呼ばれていた高知県西部・土佐清水市出身です。自然の中で奔放に育った私ですが、小学時代の修学旅行へ「足摺汽船」で1昼夜かけて高知市を訪れた時(なんと、同じ県内に修学旅行)、心地の良いショックを受けました。見るものすべてがキラキラしていて、とにかく楽しいのです。
その後、中学に入り高知市に転校することになりました。修学旅行でのワクワクを、毎日味わえるのか!と思うと、ウキウキしてなりませんでした。そして、ウキウキしながら中学~高校を高知市で過ごし、高知県立追手前高校を卒業後は、東京YMCA国際ホテル専門学校へ進みました。


根っから人と交流することが好きなんでしょうね。1972年、京王プラザホテルに就職し、ホテルマンとして社会人になりました。他人から見ると人一倍ポジティブに見えるんでしょうね。
仕事にも慣れた頃、当時京王プラザホテル画を業務提携を結んでいた、インターコンチネンタルホテルのジャパニーズレストランのホールマネージャーとして私に白羽の矢が立ちました。場所はミクロネシアサイパンインターコンチネンタルでした。当時のサイパンのホテルマンは陽気ですが、レイジー(怠け者)でした。
私の仕事は、現地のスタッフをまとめる仕事と、日本から来るVIPクラスの旅行者のサービスをしっかりと遂行することです。現地スタッフでは「アテにならない」状況でしたので、働き者のフィリピン出身者を雇い入れたりしてバランスをとっていました。
その仕事ぶりが評価を得たのか、次にインドネシアジャカルタインターコンチネンタルホテルへ派遣されることになりました。ジャカルタのホテルマンはサイパンと違ってレベルが高かったですね。当時の日本以上だったように思います。
また、私に「日本のことを知りたい」と、仕事のことだけでなく日本のカルチャーについて教えてほしいと積極的だったことがうれしかったですね。
6年間の海外赴任中、こんなことを想いました。「日本の都会は新しい発見があって楽しい。でも、バリバリ働いた後は年を重ねたら、こんな海のきれいなところでゆったり過ごすのもいいな」と。
最近では若い人たちも海外旅行をするのが一般的ですが、昔はお金と時間に余裕がある人がほとんどでした。そういった富裕層が、ゆったりと、なにか「自分自身を取り戻す時間」を過ごすために海外に訪れているような気がしていました。
そして、「この感じは故郷の高知にも似ている」とも感じていました。自然のパノラマ、陽気な人たち、美味しい料理、インドネシアのダンスミュージック「ダンドゥイット」の魅力は高知のよさこい踊りにも通じるなあ…海外リゾート地のいろいろが高知に重なるんですね。




そんなことを考えていると不思議なものです。海外派遣を終えて、しばらくすると「高知県東部・夜須町の手結(てい)にリゾートホテルをつくる話があり、総合的なマネージメントができる人間を探している」という話が舞い込んできました。もう、「はいはい」と二つ返事で引き受けさせていただきました。そのホテルが「海辺の果樹園」です。1993年の時ですからアラフォーで高知に帰ってきたことになりますね。
その後、勤務した土佐ロイヤルホテルが、私のサラリーマン人生の最後でした。
後は、小さな飲食店を経営しながら、高知の歴史文化を勉強したり、イベントに飲食店としてブースを参加したり、私自身もイベントの主催となって活動したりと高知の老若男女と交流を持つ日々を過ごし、今に至っています。主にフードコーディネーターとしての役割が多いですね。
思い出に残っているのは、高知ぢばさんセンターで行ったインドネシアフェアです。バブルの最後でしたから盛大に開催されました。3日間で9万人の来場者がありました。最近は、高知の地場産製品を都市部の皆さんに知っていただきたいと、東京の京王プラザやホテル雅叙園などで「南国土佐まつり in 東京」を開催して毎回好評を得ています。
たくさんの人に出会い、力を借りながら楽しくやりがいを持って生きていくすばらしさを私自身が実感しているのですが、「この心豊かな毎日を、多くの方に実現してもらえたら」と考えていたところ、CCRCの考えに出会いました。
この、高知版CCRCで海外赴任時代に描いていた青写真をぜひ実現したいと考えています。